この作品は、1960年代のヴォーギングなど、アメリカのクィア・コミュニティでのダンスカルチャー及び2016年にフロリダ州オーランドのゲイナイトクラブで起きた銃乱射事件の二つを基に作品を構成している。オーケストラの中央には、アクティビスト(役)のソリストがメガフォンを持って座り、ヒラリー・クリントンやレディ・ガガなど、著名な政治家やアーティストのクィアの人々に向けた言説から、アート・アクティビズムを行う試みである。
私は現在、大学の博士研究員として、ゲイタウンにおいてフィールド調査をおこなっているが、クィアにとって踊ることは今もなお重要な意味がある。前述のオーランドのゲイクラブ銃乱射事件でも、犠牲者の追悼のために、ロンドンでヴォーグを踊り続ける動画が、SNSで急速に拡散された。ヴォーグは、1960年代アメリカの都市部で「ボール・ルーム」と呼ばれる、ブラックコミュニティやラテンアメリカ人のクィア・コミュニティの中で生まれたダンス・ムーブメントであり、ヴォーグを踊ること(=ヴォーギング)は、自己表現とアイデンティティの解放を意味する。クィアにとって、ヴォーグとは、人種やLGBTIQ+コミュニティに対する差別や偏見に対する抵抗であり、反逆である。
私はヴォーグを作品に落とし込むために、Vogue-Femme(Dramatics)のダンス動画を分析し、一つ一つ動きに対応させた響きのモーメントを作り出した。それらは打楽器のAnvilによって区切られる仕切りの中で、クィアの人々に向けた政治家やアーティストの細切れにされたスピーチと共に提示され、強迫的に繰り返される。さらに、LGBTの象徴でもあるレインボーフラッグがヒッピームーブメントからも参照されたことから、私の過去の作品から「極彩色」(ヒッピーの楽園クリスチャニアをテーマに作曲)、ゲイ・アイコンであるジュディ・ガーランドの「Somewhere over the rainbow」を引用し、平和と愛、そして"You are not alone."のメッセージと共に、作品のアクティビズム性はより強調される。
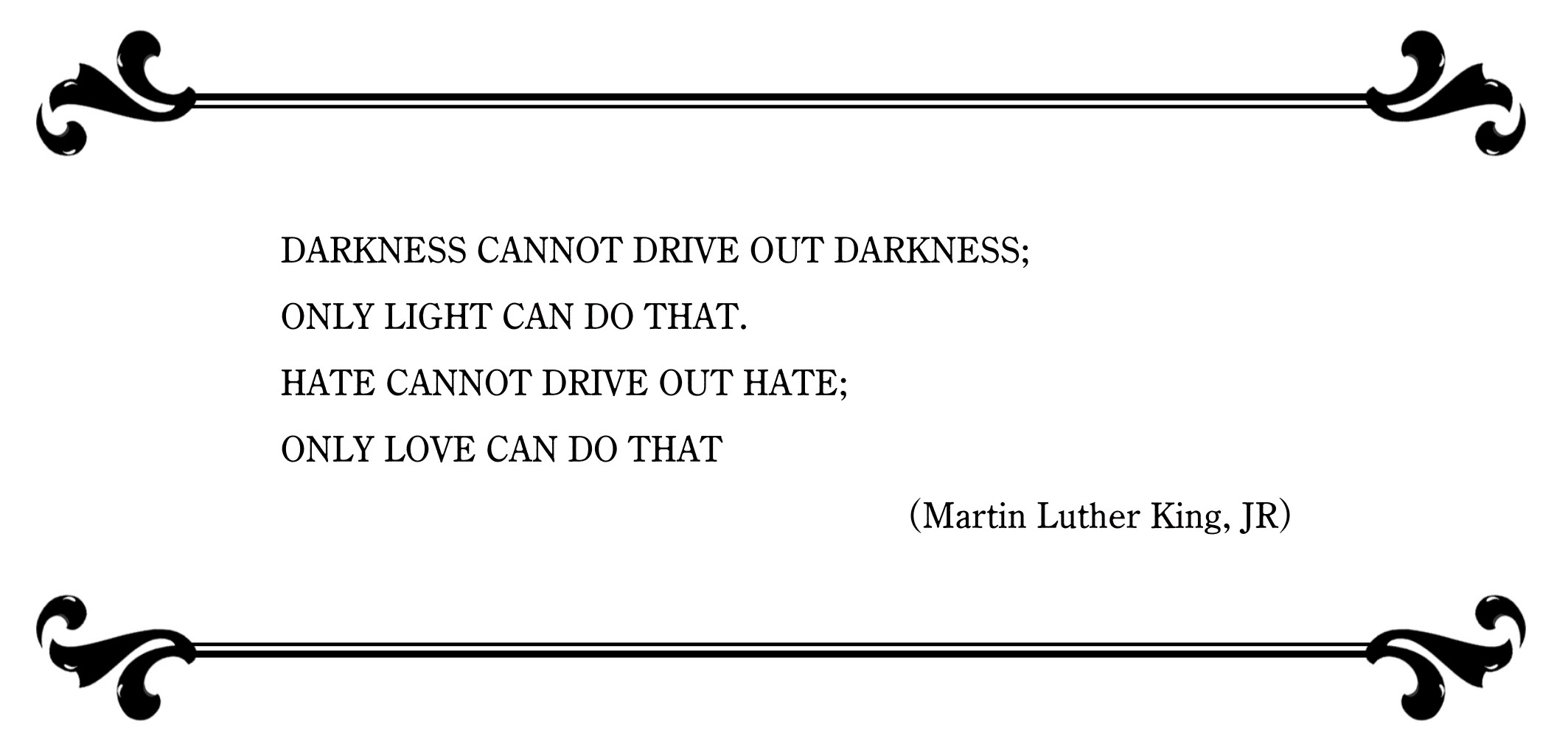
私は、言葉と音楽の力を信じている。この作品は、「私」の言説である。


